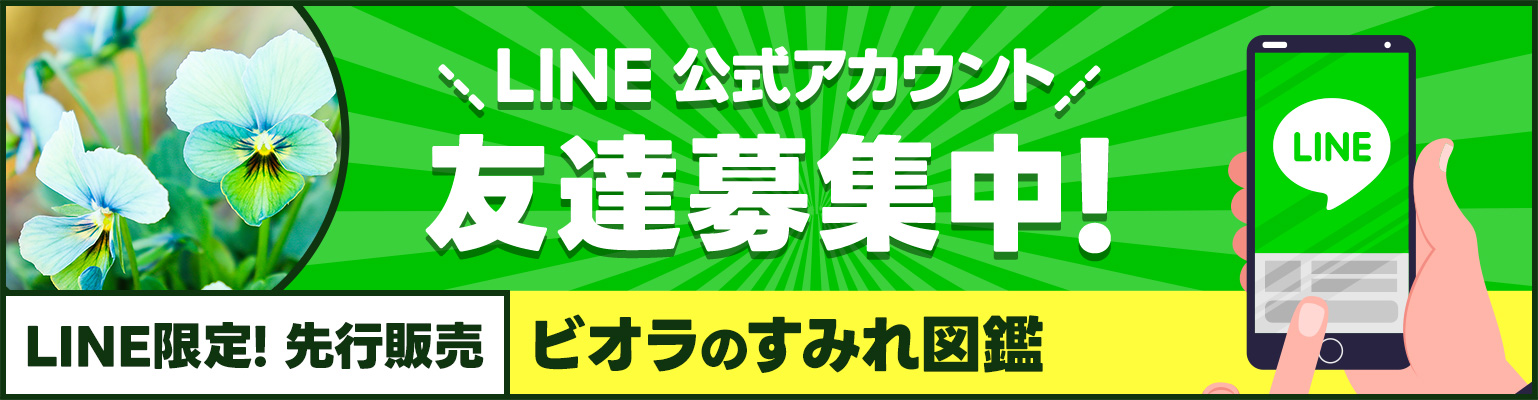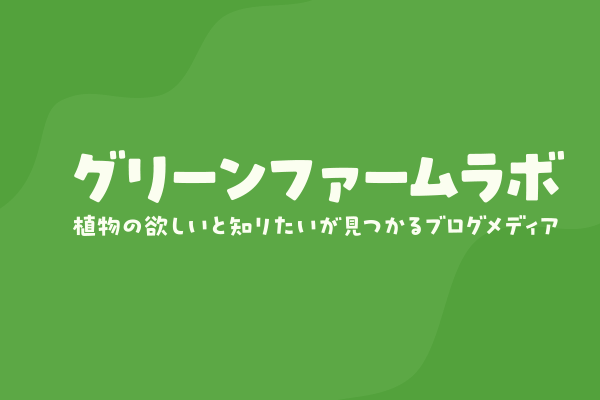はじめに
はじめに

怖い話が関わる植物といえば柳や彼岸花を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。昔からの言い伝えや物語など、日本のホラー業界におけるモチーフにもなっていますね。
また、身近にある怖さといえば毒性の植物が思い浮かびます。今年6月、北海道大学構内で国内未確認の猛毒植物であるジャイアント・ホグウィードが発見されたニュースがありました。他にも、キジムナーという精霊が宿る多幸の木として人気のあるガジュマルの別名は「絞め殺しの木」という不穏なもの。これはガジュマルに巻き付かれた植物がその締め付けの強さにより枯れてしまうことに由来しています。
このように「怖い」にも種類がありますが、身近なものから一生関わりたくないものまで植物にまつわる話を少ししてみましょう。
花を摘むと手が腐る!?「いわく」のある植物たち
どうして?不吉ないわれのある彼岸花

秋分の日を中心とした秋彼岸頃に咲くことからその名がついた彼岸花。「彼岸」は「向こう岸」という意味で、彼岸を「あの世」と解釈して亡くなった人々を供養するためにお墓参りをしています。古くからお墓の近くに彼岸花を植えることもありました。まだ土葬をしていた頃、ネズミやモグラなどが遺体を荒らすことを彼岸花が持つ毒で避けようとしたためです。彼岸花は花、葉、茎、根の全てに毒を持つ植物です。特に毒性物質を多く含むのが球根。ネズミやモグラなどが齧ると球根1つで1500匹が死ぬとも言われています。ちなみに球根1つを人間が摂取しても死には至りませんが嘔吐や呼吸困難を引き起こすことがあります。お子様やペットが齧らないように注意して下さいね。
さて、彼岸花を摘むと手が腐ると聞いたことはないでしょうか。これは上記のように毒性があることが由来の別名「テクサレ」という別名からかもしれません。彼岸花には1000を超える異名があるとされています。曼珠沙華やシビトバナが有名ですが、幽霊花、親死ね子死ね、地獄花など穏やかではないものもあります。異名を色々つけたくなるほど昔から身近で彼岸花に魅了されていたのでしょう。
最近あまり聞かない…元祖心霊スポット?
 柳の下に現れる幽霊は江戸時代の奇談集「絵本百物語」の柳女が原型とされていますが、それ以前から柳は霊の宿る木と考えられていました。日本のみならず中国でも柳には霊的なイメージがあり、棺を柳の木から作るそうです。庭に植えるととても素敵なのですが、敷地内に植えると家族関係の崩壊、精神を病む、お金が貯まらないなどという言い伝えがある凶木とされています。
柳の下に現れる幽霊は江戸時代の奇談集「絵本百物語」の柳女が原型とされていますが、それ以前から柳は霊の宿る木と考えられていました。日本のみならず中国でも柳には霊的なイメージがあり、棺を柳の木から作るそうです。庭に植えるととても素敵なのですが、敷地内に植えると家族関係の崩壊、精神を病む、お金が貯まらないなどという言い伝えがある凶木とされています。
人の潜在能力を引き出す強烈な薬物
 ペヨーテは観賞用として流通し、日本では烏羽玉と呼ばれるサボテンの一種。メキシコの原住民ウィチョル族が宗教儀式に使用することも知られています。一定量のペヨーテを摂取すると化学物質メスカリンが作用して強烈な幻覚を何時間も見ます。その幻覚は極彩色で風景や空が幾何学模様に見える異次元的な世界だといいます。ウィチョル族はペヨーテを「神の肉」と呼んで大切にしてきました。しかし1960年代、ヒッピーカルチャーの流行により一部若者の間で向精神薬として使用されてしまいました。規制幻覚作用のある薬物ながら常習性は低く中毒性薬物とは異なりますが、日本ではその成分は規制の対象となっています(育てるのは問題ありません)。
ペヨーテは観賞用として流通し、日本では烏羽玉と呼ばれるサボテンの一種。メキシコの原住民ウィチョル族が宗教儀式に使用することも知られています。一定量のペヨーテを摂取すると化学物質メスカリンが作用して強烈な幻覚を何時間も見ます。その幻覚は極彩色で風景や空が幾何学模様に見える異次元的な世界だといいます。ウィチョル族はペヨーテを「神の肉」と呼んで大切にしてきました。しかし1960年代、ヒッピーカルチャーの流行により一部若者の間で向精神薬として使用されてしまいました。規制幻覚作用のある薬物ながら常習性は低く中毒性薬物とは異なりますが、日本ではその成分は規制の対象となっています(育てるのは問題ありません)。
感情を刺激する!恐ろしい別名をもつ植物
植物には一般名のほかに、特徴や歴史、見た目などから別名がつけられていることが多いです。しかし、その中には恐ろしいものもあります。一例をご紹介いたします。
●オオミフクラギ・・・「自殺の木」 インドから東南アジアに自生しているオオミフクラギ、種子にケルベリンという有毒成分を多く含み摂取すると致死的な不整脈や高カリウム血症を引き起こす可能性があることからこう呼ばれている。
インドから東南アジアに自生しているオオミフクラギ、種子にケルベリンという有毒成分を多く含み摂取すると致死的な不整脈や高カリウム血症を引き起こす可能性があることからこう呼ばれている。
●ドクウツギ・・・イチロベエゴロシ(一郎兵衛殺し) その猛毒が人を死に至らしめることから名付けられました。ドクウツギは、トリカブト、ドクゼリと並んで日本三大有毒植物の一つとされており、特に果実は見た目が美味しそうに見えるため、誤食による事故が多く報告されています。
その猛毒が人を死に至らしめることから名付けられました。ドクウツギは、トリカブト、ドクゼリと並んで日本三大有毒植物の一つとされており、特に果実は見た目が美味しそうに見えるため、誤食による事故が多く報告されています。
●マンチニール・・・死のりんご 「世界で最も危険な樹木」としてギネス世界記録にも認定されている植物です。その果実がリンゴに似ていながらも猛毒を持つことに由来します。樹液、葉、果実、樹皮など、植物全体に強い毒性を持っています。果実を摂取すると、口腔内や喉のただれ、内臓へのダメージを引き起こし、最悪の場合死に至ります。
「世界で最も危険な樹木」としてギネス世界記録にも認定されている植物です。その果実がリンゴに似ていながらも猛毒を持つことに由来します。樹液、葉、果実、樹皮など、植物全体に強い毒性を持っています。果実を摂取すると、口腔内や喉のただれ、内臓へのダメージを引き起こし、最悪の場合死に至ります。
●こんにゃく・・・Devil’s Tongue(デビルズタン) こんにゃくの花をみたことがありますか?縦長く伸びた赤黒い姿はぎょっとします。その独特な花の形状からこう呼ばれています。
こんにゃくの花をみたことがありますか?縦長く伸びた赤黒い姿はぎょっとします。その独特な花の形状からこう呼ばれています。
 美しき呪い──不吉な花言葉をもつ花々
美しき呪い──不吉な花言葉をもつ花々

花には、贈る人の想いや季節の移ろいを映す美しさがあります。しかしその裏には、時に恐ろしい意味や物語が隠されていることをご存じでしょうか?
今回は、見た目の華やかさとは裏腹に「不吉な花言葉」を持つ花々をご紹介します。美しさに潜む闇に、少しだけ触れてみませんか。
死や滅亡を象徴する花
 ● スノードロップ:「あなたの死を望みます」
● スノードロップ:「あなたの死を望みます」
雪のように儚い姿とは裏腹に、恋人の死を悼む伝説が由来。贈る相手には注意が必要です。
● 睡蓮(スイレン):「滅亡」
水面に浮かぶ優雅な姿が、古代文明の終焉と重ねられたことからこの花言葉が生まれました。
嘘・裏切り・偽りの象徴
 ● イヌホオズキ:「嘘つき」
● イヌホオズキ:「嘘つき」
毒性を持つことから、見た目に騙される危険性を暗示しています。
●白いゼラニウム:「偽り」「私はあなたの愛を信じない」
恋の駆け引きに使われることもある、少し怖い花言葉。
●黄色いカサブランカ:「裏切り」
聖書に登場するユダの象徴として、裏切りの色とされる黄色が意味を変えました。
復讐・呪い・憎悪を秘めた花
 ●クロユリ:「復讐」「呪い」「憎悪」
●クロユリ:「復讐」「呪い」「憎悪」
戦国武将・佐々成政がこの花を使って愛人を処刑したという逸話が残っています。
●トリカブト:「復讐」「人間嫌い」
猛毒を持つこの花は、古くから呪術や毒殺に使われてきました。
怒り・嫉妬・敵意を映す花
 ● 紫の芍薬:「憤怒」
● 紫の芍薬:「憤怒」
芍薬は色によって花言葉が異なり、紫だけが怒りを象徴しています。
●オトギリソウ:「恨み」「敵意」
平安時代の兄弟の悲劇が由来。切り傷に効く薬草としても知られていますが、名前の由来は物騒です。
妖しき魅力と危険を秘めた花
 ●月下美人:「危険な快楽」
●月下美人:「危険な快楽」
一夜限りで咲き、妖艶な香りを放つこの花は、まさに“美しき罠”。
●マンサク:「呪文」
春先に咲くこの花は、魔術や霊的な力を連想させる不思議な存在です。
花言葉の裏側にある物語
花言葉は、単なる意味の羅列ではなく、文化や歴史、伝説が織り込まれた“言葉の花束”です。
不吉な花言葉を知ることで、花に込められた物語の深さに気づくことができます。
美しさに潜む闇を知ることで、花の魅力はさらに増すのかもしれません。
意外と多い?身近に潜む有毒植物の実態を解説
有毒植物は、その全体または一部に毒を持つ植物のことです。誤って食べると、嘔吐、下痢、手足のしびれ、呼吸困難などの症状を引き起こし、死亡する可能性もあります。特に春から初夏にかけて、食用と間違えやすい有毒植物による食中毒が多く発生するため注意が必要です。
皆様の身の回りにも有毒植物がありますが意外と知られていません。有毒植物をいくつか紹介します。
有毒植物(野外編)
●トリカブト (別名:ウズ、カブトバナ、カブトギク)
(別名:ウズ、カブトバナ、カブトギク)
自生地:日本全土、山中のやや湿った樹木の下
毒の部位:全部(根、茎、葉、花、種子など)、とくに根に強い毒がある
症状:しびれ、嘔吐、下痢、不整脈、呼吸困難、麻痺
間違えやすい植物:ニリンソウ、モミジガサ(シドキ)
●バイケイソウ、コバイケイソウ自生地 高山の湿地等
 毒の部位:全草
毒の部位:全草
症状:吐気、嘔吐、腹痛、手足唇の痺など
間違えやすい植物:オオバギボウシ、ギョウジャニンニク
●ハシリドコロ 自生地:樹陰の湿地等
自生地:樹陰の湿地等
毒の部位:全草
症状:瞳孔散大、脱力感、歩行困難、幻覚など
間違えやすい植物:フキノトウ
●ドクゼリ (別名:オオゼリ、イヌゼリ)
(別名:オオゼリ、イヌゼリ)
自生地:沼や小川などの水辺
毒の部位:全部、春は根に毒成分が多い
症状:大量の嘔吐、下痢、瞳孔散大、激しい痙攣
間違えやすい植物:セリ
有毒植物(家庭編)
●チョウセンアサガオ (別名:マンダラゲ、ナンバンアサガオ、トウナスビ、バラモンソウ)
(別名:マンダラゲ、ナンバンアサガオ、トウナスビ、バラモンソウ)
(注意!) 近年、たいへん人気のあるエンゼルストランペットも、チョウセンアサガオの仲間で同じような毒をもつので、取り扱いに注意が必要です。
自生地 荒地、1年草で、ラッパの様な形の花が咲きます。観賞用として一般流通しています。花の色は白、黄、オレンジなどです。
毒の部位:全部、とくに根、種子に強い毒がある
症状:興奮、幻覚、のどの渇き、瞳孔散大
間違えやすい植物:ゴマ、ゴボウ
●ジャガイモ ジャガイモの新芽や日光にあたって表面が緑色になったところには、ソラニンという毒が多く含まれています。「発芽したばかりだから大丈夫!!」とか「少ししか変色していないから大丈夫!!」といった過信は禁物です。発芽していたり緑色に変色したものをそのまま食べてしまうと、嘔吐、腹痛、めまいといった症状がでます。
ジャガイモの新芽や日光にあたって表面が緑色になったところには、ソラニンという毒が多く含まれています。「発芽したばかりだから大丈夫!!」とか「少ししか変色していないから大丈夫!!」といった過信は禁物です。発芽していたり緑色に変色したものをそのまま食べてしまうと、嘔吐、腹痛、めまいといった症状がでます。
●福寿草(フクジュソウ) 早春に芽を出し、鮮黄色の花をつける福寿草は、縁起の良い花としてお正月に飾られます。そんな福寿草にも毒があります。とくに新芽は、フキノトウと間違えやすく、食べて死亡した例も報告されています。症状は、嘔吐、呼吸困難、心臓麻痺などです。
早春に芽を出し、鮮黄色の花をつける福寿草は、縁起の良い花としてお正月に飾られます。そんな福寿草にも毒があります。とくに新芽は、フキノトウと間違えやすく、食べて死亡した例も報告されています。症状は、嘔吐、呼吸困難、心臓麻痺などです。
●ポインセチア 冬の定番の花、ポインセチアは、緑と赤の色合いが大変きれいな花です。この花の茎などからにじみ出る白い液には注意が必要です。この白い液には、フォルボールという毒成分が含まれており、皮膚炎や下痢、嘔吐、目につくと結膜炎の原因になります。
冬の定番の花、ポインセチアは、緑と赤の色合いが大変きれいな花です。この花の茎などからにじみ出る白い液には注意が必要です。この白い液には、フォルボールという毒成分が含まれており、皮膚炎や下痢、嘔吐、目につくと結膜炎の原因になります。
●スズラン 春の穏やかな日にどこから漂ってくるスズランの香りは、こころに安らぎを与えてくれます。ところがスズランの毒は猛毒で、花にも毒が含まれます。新芽をギョウジャニンニクと間違えて食べた例があります。食べると、嘔吐、頭痛、視覚障害、血圧低下などの症状があらわれます。
春の穏やかな日にどこから漂ってくるスズランの香りは、こころに安らぎを与えてくれます。ところがスズランの毒は猛毒で、花にも毒が含まれます。新芽をギョウジャニンニクと間違えて食べた例があります。食べると、嘔吐、頭痛、視覚障害、血圧低下などの症状があらわれます。
●スイセン 観賞用としてごく一般的に栽培されていますが、これにはかなり強い毒成分が含まれています。葉がニラと似ているため、誤って食べて死亡した例が報告されています。花瓶挿しにした場合、残った水も危険です。症状は、嘔吐、胃腸炎、神経麻痺、血圧低下、心不全などがあらわれます。
観賞用としてごく一般的に栽培されていますが、これにはかなり強い毒成分が含まれています。葉がニラと似ているため、誤って食べて死亡した例が報告されています。花瓶挿しにした場合、残った水も危険です。症状は、嘔吐、胃腸炎、神経麻痺、血圧低下、心不全などがあらわれます。
●アジサイ 一般の家庭でも生け垣等として栽培されることの多い植物ですが、葉や花を食べると食中毒症状を引き起こします。飲食店で料理の飾りに添えられたアジサイの葉を間違って食べ、食中毒となった例があります。
一般の家庭でも生け垣等として栽培されることの多い植物ですが、葉や花を食べると食中毒症状を引き起こします。飲食店で料理の飾りに添えられたアジサイの葉を間違って食べ、食中毒となった例があります。
(おまけ)変なルックスの植物たち3選
●アリストロキア・ギガンテア
 ウマノスズクサ科
ウマノスズクサ科
ブラジル原産常緑つる性植物。花に見える部分は萼で長さ30cmほどになる。産毛の生えた萼の表面は赤褐色に白い網目状の模様が入り、独特な匂いで虫を誘います。
●アリストロキア・サルバドレンシス
 ウマノスズクサ科
ウマノスズクサ科
エルサルバドルに自生する常緑小低木。どう見たってダースベイダー。目に見える2つの穴から中に虫が入って受粉する。
●ラフレシア 腐った肉のような匂いがする世界最大の花として有名な、葉緑体を持たず自力では成長できない完全寄生植物。宿主から水分や養分を収奪し最大1mの花を咲かせるとんでもない花である。しかもちゃっかり種をもつ実を結ぶ。キャベツほどの大きさの。怖い。ラフレシアは宿主からDNAも盗んでいるが、それをどのように活用しているかはまだ謎らしい。
腐った肉のような匂いがする世界最大の花として有名な、葉緑体を持たず自力では成長できない完全寄生植物。宿主から水分や養分を収奪し最大1mの花を咲かせるとんでもない花である。しかもちゃっかり種をもつ実を結ぶ。キャベツほどの大きさの。怖い。ラフレシアは宿主からDNAも盗んでいるが、それをどのように活用しているかはまだ謎らしい。
まとめ
苦手だと思う「怖い」ジャンルや興味を持ったものはありましたでしょうか。見たこともないものから家にある身近な植物まで本文では色々出てきましたが、もちろんこれらはほんの一部に過ぎません。もし心を動かすきっかけになりましたら、これから色々調べて怖くも面白い植物の世界に一緒に浸っていただけたら嬉しいです。